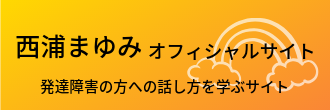発達障害 話し方心理カウンセラーの西浦まゆみです。
公園の前を歩いていると、
小学生くらいの子どもがかけっこか鬼ごっこをしていました。
その時に22歳になる発達障害の息子の
公園で遊んでいる子どもたちと同じくらいの頃のことを
不意に思い出しました。
親戚の集まりかなんかの時に、
発達障害の息子が同じくらいの従兄弟たちと鬼ごっこをしている時に
甥っ子から苦情を言われました。
発達障害の息子が
「鬼でもないのに、追いかけてくる、鬼の時に逃げてばかりいる」と。
その時の私は、なんでそんなことを発達障害の息子がするのかわからず、
怒っていました。
その当時の発達障害の息子はうまく言葉で伝えることが苦手で
「うん」「わからない」「知らない」「ごめんね」くらいしか話さなかったので、
私は発達障害の息子のことがよくわからず、イライラしていました。
後で分かったことですが、
その時の発達障害の息子は鬼ごっこのルールが分からず
ただ、追いかけっこをしているだけと思っていたようです。
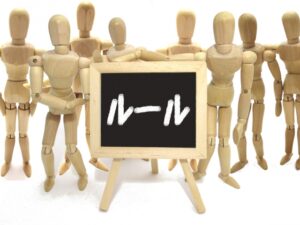
発達障害のわが子によっては、私の息子と同じように
ルールをわからないか、勘違いをして遊びに参加していることがあります。
そして、周りからなんか違うと指摘をされることがあります。
子どもの世界はある意味、大人よりも厳しい時があります。
ルールを守れない子どもはいけない、そんな子どもとは遊びたくない
何でルールを守れないんだっと厳しく言われることもありますよね。
そんな時に、発達障害のわが子は自分の気持ちをうまく表現できなくて
悲しい思いをすることがあります。
だから、発達障害のわが子が自分で言えるように伝え方を教えたり、
事前に主だった遊び方を教えておくのも有効です。
私たち親は、発達障害のわが子がしているから、
分かってしていると思いがちです。
また、誰もがしたことはある鬼ごっこやジャンケンなどは
私たち親は無意識に知っていると思ってしまいます。
しかし、発達障害のわが子は知らないでしていることが多いものです。
なので、発達障害の子どもを持つ親のあなたが、
ジャンケンのルールや鬼ごっこなどの遊びを発達障害のわが子としながら、
教えたり、知っているのかの確認をしたりすることですね。
そして、発達障害のわが子に「遊びのルールを教えて」との伝え方や
自分の思っている遊びのルールであっているのかの確認の仕方を教えることです。
意識してくださいね。
発達障害のわが子への話し方や接し方を詳しく知りたい方は
下記をクリックしてください。
発達障害 話し方無料メールセミナー