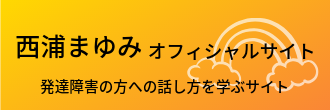発達障害 話し方心理カウンセラーの西浦まゆみです。
発達障害のわが子によっては不安を強く感じすぎることがあります。
これは、発達障害のわが子の心と身体が過剰に反応するためですね。
なので、心だけ、身体だけフォローしても不安は改善しません。
発達障害のわが子の心と身体をフォローしていくことで
不安が改善していきます。
発達障害のわが子の心の問題は、
認知の歪みからくる思考癖とストレス耐性の低さです。
身体の問題は、不安や恐れに過剰に反応する脳の扁桃体の暴走と、
その扁桃体を抑制する働きのある脳の前頭前野の機能低下です。
脳の扁桃体は感情を司っていて、前頭前野は理性を司っています。
危険を察知するために、
脳は理性よりも感情を司る扁桃体に情報がいくようになっています。
なので、不安や恐れの感情は誰にでもあるのですね。
通常であれば、不安や恐れの感情があっても、
理性を司る脳の前頭前野が働いて過剰な不安や恐れを抑制するのですが、
発達障害のわが子によっては、
ストレス耐性が低いためにストレスによって脳の前頭前野の働きが鈍っています。
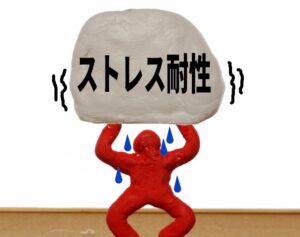
そのために、扁桃体への刺激を抑制できずに過剰に反応してしまい、
発達障害のわが子の不安や恐れは大きくなっていくのですね。
なので、発達障害のわが子の不安や恐れを和らげるには、
認知の歪みを修正して、わが子にあったストレスにしてストレス耐性を上げ
扁桃体への暴走とストレス過剰で前頭前野の機能低下を改善することです。
その1つの対応として、
発達障害のわが子に親のあなたが見通しを持たせた話し方を意識的にすることです。
発達障害のわが子が不安を感じるのは、
見通し力が弱いために何があるのかわからない不安や恐れがあるからです。
なので、発達障害の子どもを持つ親のあなたが
「こうなることがあるよ」と見通し力を持った話し方を意識的にして
発達障害のわが子に伝えることでわが子は安心感を持ちます。
例えば、明日プールの授業があるとした時に
「明日のプールの授業があるから、水着と帽子とタオルがいるよ」
「雨だったら、体育になるかもしれないから体操服も準備しておこうね」など
発達障害のわが子が行動できるように見通しを立てて伝えることですね。
そうすると、発達障害のわが子は何をしたらいいのかわかるので、安心感を持ちます。
発達障害のわが子が安心感も持つと、
扁桃体の過剰反応がなくなり、前頭前野の抑止力も働き、
過剰なストレスから適度なストレスになるので
ストレス耐性もつき不安も和らいでいきます。
意識してくださいね。
発達障害のわが子への話し方や接し方を詳しく知りたい方は
下記をクリックしてください。
発達障害 話し方無料メールセミナー