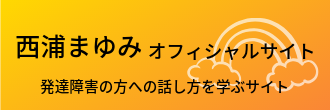発達障害 話し方心理カウンセラーの西浦まゆみです。
発達障害の二次的障害に不登校があります。
不登校の発達障害のわが子は認知の歪みによる思考が
不登校解決の妨げになっていることは少なくはありません。
その認知の歪みによる思考癖の1つに、他責思考があります。
他責思考とは、自分には責任はないと他人や状況に責任転嫁をする思考のことですね。
例えば、不登校の発達障害のわが子がルールにこだわりがあり、
学校の廊下を走らないルールなのに、
それを守らない人(生徒や教師)がいるから、学校には行きたくない。
自分はちゃんとルールを守っているのに、
守らない人が悪い、そんな学校には行きたくない、と
自分には責任はなく、ルールを守らないのが悪いという思考です。
確かに、ルールを守らないのは良くはありません。
しかし、ルールを絶対に守らなくてはいけないと言う思考があると
発達障害のわが子の心は疲弊していきます。
なぜなら、人はうっかりミスをするものなので、
気をつけていても、ルールを破る場合があるからですね。
それを、受け入れられずに発達障害のわが子は他責思考で
自分はルールを守っているから、守らない人がいるのが悪い
だから、そんな学校には行きたくないと不登校になってしまうこともあります。

他責思考があると、不登校解決が遠ざかっていきます。
ルールを守ることはいいことですが、
他人にもそれを強要することはできないからです。
しかし、他責思考のある発達障害のわが子は自分よりも相手を変えたがります。
発達障害のわが子はルールを絶対に守らせないといけない
守らないのが悪いと思っているからです。
発達障害のわが子がルールにこだわりすぎないなら、
ルールを守らないことを許せない気持ちを持つことも、
それで学校に行きたくない気持ちになることもないですよね。
なので、発達障害のわが子に
変えられることと変えられないことがあることを教えることが大切です。
人は自分のことは変えられますが、
自分以外のことは変えることはできません。
なぜなら、人はそれぞれに自分の価値観や思考があるからですね。
相手が嫌いなことを、
自分が好きだから相手も好きにならないといけないと思っていても
相手を変えることはできないですよね。
それよりは、自分はこれ好きだけど、
相手は嫌いなんだなと思考変えることはできます。
それと同じで、発達障害のわが子がルールを守ることにこだわりが強すぎて、
それを他者に強要してしまい、ルールを守らない人がいる学校が悪いと
自分では変えられないことを求めていると
不登校の解決の妨げになってしまいます。
なので、まずは変えられるものと変えられないものを知ること、
不登校の発達障害のわが子の他責思考を緩めていくことが大切です。
意識してくださいね。
発達障害のわが子への話し方を詳しく知りたい方は
下記をクリックしてください。
発達障害 話し方無料メールセミナー