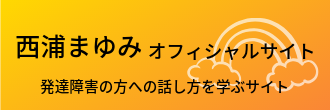発達障害 話し方心理カウンセラーの西浦まゆみです。
昨日、今年社会人になった発達障害の息子が仕事から帰省して、
呼ばれて玄関に行くと、なんと蛇が息子の履物の後ろに・・・。
予想だにしていない事態にびっくり。
思わず体が後ずさっていきました。
発達障害の息子に蛇の対処を懇願しましたが、
発達障害の息子も蛇は怖く出来ないと。
二人して固まったまま蛇を見つめていたら、蛇が動き出したので、
私はとっさに発達障害の息子に近所の人に助けを求めてきてと叫んでいました。

それからの発達障害の息子は素早かったです。
近所の方を連れて来てくれて、近所の方が蛇の対処をしてくれて、
私たち親子はホッと一息ついたのです。
暫くは、ドキドキが収まらなかったです。
近所付き合いや町内の付き合いのことを特に意識したのは
発達障害の息子が発達障害とわかってからです。
発達障害の息子が偏見に見られないように、
発達障害の息子が近所の方の顔が分かるようにと思い、
発達障害の息子と挨拶から始めて行きました。
町内会の活動や子供会行事などは参加出来る限りは
発達障害の息子と参加していきました。
数年に1回町内の班長になった時、
月1回の町内会の集まりに発達障害の息子と一緒に参加して、
配りものも一緒の分けて、自分の班宅を一緒に配っていきました。
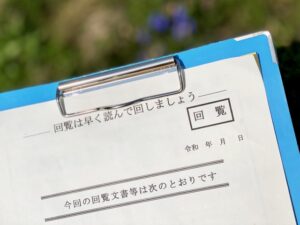
いつの間にか発達障害の息子は自分で近所の人に挨拶が出来るようになり
近所の人と会って声掛けが出来るようになっていました。
たまに、近所の人と会って挨拶をしたよと発達障害の息子が話をしてくるようになりました。
近所付き合いと言っても、挨拶をする程度の付き合いです。
挨拶+ひと言、ふた言を話す程度です。
今回は、ご近所さんにも助けられ、発達障害の息子にも助けられました。
発達障害の息子がご近所さんに説明して連れてくることが出来て良かったです。
発達障害の子どもを持つ親のあなたは近所付き合いをどう思っていますか?
何となく面倒、どう思われるか不安など色々なことを思っているかもしれませんね。
人は人との関わり合いの中で色々なことを学んいきます。
最初の人間関係は親子関係です。
その次が家族関係、血族関係、友人関係や地域関係、社会関係とその輪が広がっていきます。
人は知らないと警戒します。
自分の分からないものは受け入れきれないのですね。
なので、近所付き合いといっても特別なことをするのではなく
「挨拶」をして顔を知る、そして自分たちの輪が少し広がるのを意識するだけです。
ただ、近所付き合いでも苦手な雰囲気の方はいますよね。
そんな時は無理をせず、
発達障害の子どもを持つ親のあなたや発達障害のわが子の直観(挨拶が出来そう、
会釈が出来そう、この人は挨拶出来そうもないなど)に従ってみるのもいいでしょう。

発達障害のわが子の輪を少し広げるための近所付き合いは「挨拶」からです。
発達障害のわが子は最初は挨拶は出来ません。
タイミングやどう接していけばいいのか分からないからです。
定形発達の子どもであれば、自然に身につくことも
発達障害のわが子には意識しないと身につかないのです。
なので、発達障害のわが子には意識した話し方で伝えていかなければ伝わりません。
この時の話し方は「体験を通じた見本を示す話し方」です。
発達障害の子どもを持つ親のあなたが見本を示しながを
発達障害のわが子に伝える話し方ですね。
そしてスモールステップも大切です。少しづつ段階を得る方法ですね。
近所の人への「挨拶」では親のあなたが一緒の時に見本を示します。
この時に目が合ったら、目の前の距離になったらなどの距離感やタイミングも
具体的に話していきます。
「おはようございます」「こんにちは」など声に出して挨拶をすることも
発達障害の子どもを持つ親のあなたが見本を示します。
発達障害の子どもを持つ親のあなたが見本を示しながら
発達障害のわが子が慣れて行ったら、次は発達障害のわが子が挨拶をしていく
発達障害のわが子が挨拶が苦手な時は会釈だけでもいいからするなど
発達障害のわが子に合わせた段階を踏んでいくことが必要になります。
試してくださいね。
もっと詳しく発達障害のわが子との話し方をしりたい方は
「発達障害 話し方無料メールセミナー」で知ることが出来ます。
下記をクリックして下さい。
https://nishiuramayumi.com/mailmagazine